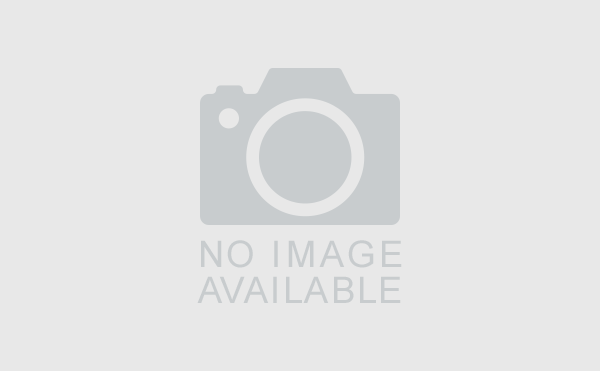<開催報告>SRセミナー2024第1回「NPO/NGOこそ人権を広く深く捉えて取り組もう!~具体的な活動や運営の事例から学ぶ人権課題の取り組み方~」
2024年7月9日(火)に、2024年度第1回SRセミナー「NPO/NGOこそ人権を広く深く捉えて取り組もう!~具体的な活動や運営の事例から学ぶ人権課題の取り組み方~」をオンライン開催し、約22名の皆さまに参加いただきました。
世界で人権尊重の重要性が益々高まっている中、日本社会では“ビジネスと人権”は活発に議論される一方で、多様な分野で活動しているNPO/NGOは人権に対する理解や行動に難しさを感じています。ビジネスのみならず幅広い意味での人権課題について、ゲストから「非人道性」「当事者性」「加害者性」のテーマを持つ具体的な取組事例を紹介いただき、参加者とともにNPO/NGOが自らの組織で取り組むSR(社会責任)について討論しました。
<登壇者>
話題提供:
吉澤有紀(認定NPO法人難民を助ける会 事務局次長・広報コミュニケーション部長)
中西由起子(認定NPO法人DPI日本会議 副議長)
門間尚子(特定非営利活動法人mia forza 代表理事)
進行:
松原裕樹(NNネット幹事/特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター 専務理事・事務局長)
<記録>
●セッション1:事例紹介「人権課題に取り組むNPO/NGOの活動と運営」
発題①「『悪魔の兵器』から人の命と将来を守る」/吉澤有紀(認定NPO法人難民を助ける会 事務局次長・広報コミュニケーション部長)

悪魔の兵器と呼ばれる非人道性の高い地雷について、その廃絶に向けた取組と仕組みづくりについて紹介する。普段は広報を担当している、廃絶のためには市民運動が大事なので、広報の視点からもお話したい。
AARは難民支援を原点に活動しており、人道的危機にさらされた人々への緊急支援と未来を切り開くための長期的な支援を6つの分野に注力して行っている。現在は18の国と地域で活動しており、ウクライナ、シリア、アフガニスタン、ウガンダで地雷対策の事業を行っている。
地雷とは、地中や地表に設置され、人や車が通ったり、触れたりすることによって爆発するように設計された爆弾類で、典型的な防衛兵器、敵の進行を遅らせる、見方が攻撃しやすい方向へ敵を誘導する、陣地を防御する役目を持つ。地雷の特徴は、製造が安易かつ安価、無休で防御、小火器などほかの対人兵器の補足手段、敵に重大な心理的効果を与える、持ち運びが便利、迅速かつ大量の散布も可能。悪魔の兵器と呼ばれている理由は、無差別性、半永久性、残忍性に起因する。
地雷使用禁止に向けた市民社会の動きとして、地雷は政治・軍人問題ではなく市民が関わるべき人道問題であるという認識のもと立ち上がった地雷禁止に向けたキャンペーンが起こり、1992年にICBL(International Campaign to Ban Landmines)が設立した。そして、ICBL・ICRC(赤十字国際委員会)にて、既存の枠組みで全面禁止実現を目指すも、強化されるも禁止に至らず、人道よりも防衛重視、全会一致の壁という困難さがあり、カナダなど賛同国とICBLで何とかしようという道を模索し続ける。その結果、オタワ条約が1997年にオスロで採択、オタワで署名、1999年3月に発効された。対人地雷の使用、貯蔵、生産、移譲等を全面的に禁止するもの。2022年で締約国が164ヶ国、日本も1997年に署名、1998年に批准している。オタワ・プロセスの意義としては、超大国・大国抜きの賛同国だけで特定兵器の廃絶を目指し、全会一致方式の意思決定システムでない軍縮交渉、市民社会がキャンペーンを主導、対人地雷のみに焦点を絞って政治家等に働きかけたことが挙げられる。また、その一方で、それらのやり方に批判的な意見もある。
AARとしては、イギリスの専門団体と連携した地雷除去、被害に遭わないための地雷回避教育、地雷被害者への支援を行っている。1997年の地雷廃絶国際キャンペーン(ICBL)に参加し、政府への働きかけを行った。一般の方にも呼びかけて、世論を高めるという働きかけとして、地雷廃絶キャンペーンの絵本刊行、長野オリンピックの聖火ランナーに地雷被害者を招聘、マスコミと連携したキャンペーン、全国子どもサミットを展開した。
市民運動への応用可能性として、反戦平和運動と一線を画すこと、シングル・イシューに絞ってきわめて戦略的に選択したこと、不一致の中の一致点を探して分裂しなかったこと、サバイバーや汚染地の声・証言が運動の原点であったこと、クラスター兵器連合と共同したこと、意欲のあるミドル・パワー(中堅国家)とパートナーシップを組んで進めたことが特徴にある。
発題②「障害当事者からみた差別と合意的配慮」/中西由起子(認定NPO法人DPI日本会議 副議長)

DPI日本会議は、障害当事者の権利擁護団体として活動している。
何が差別かについて、私は生まれたときから障害者、自然に自分にはできないことがあり、そういう事実を受け入れてきたので、差別意識が弱かった。差別とは、異なる取り扱い(障害を理由に他の人と違う扱いをする場合)と、合理的配慮の欠如(実質的な平等を確保するには、一定の配慮が必要だが、その配慮をしない場合)がある。
障害を理由とした異なる扱いとして、無知と誤解、偏見、無理解、が差別に繋がっている。差別のもの差しとして、どこまでが許されて、どこから差別なのか、何が求められる配慮なのか、その判断は人それぞれでもあるので難しい。そのため、そのもの差しが必要ということで、障害者団体が運動して障害者差別禁止の法律をつくろうという動きになった。当初は差別禁止の法律を目指していたが、政府にあがって法律になった際には、差別を解消するという政府のあいまいな表現で、障害者差別解消法となってしまった。
障害者差別解消法は、2016年に施行され、不当な差別的取り扱いを禁止し、合理的配慮の提供を求めている。これらは、行政だけでなく民間事業者も対象で、当時は民間事業者は努力義務であったが、2024年4月からは全ての事業者が義務化され、ボランティア活動する団体やNPOも事業者に含まれる。
合理的配慮の基本ポイントは、障害のある人の意見を聞く、個別のニーズに対応する、思いやりではないこと。当事者が合理的配慮を要求した時に、提供する側の対応するポイントとして、よく「もし何かあったら」「安全のため」「特別扱いはできない」「前例がない」「マニュアルにない」と対応を断ることがあるが、合理的配慮を提供しないことは差別になる。
合理的配慮義務の欠如=差別となっているが、配慮義務を怠っても差別ではないのではないか?どうして障害者だけ、そんなに特別に配慮しなくてはいけないのか?という声もある。しかし、これらの背景として、社会資本の不公平な配分と利用格差があること、文明の片面的な進歩は差別を拡大すること、社会参加のスタートラインが平等になっていないことがある。だから、合理的配慮が必要となる。
アクセシビリティと合理的配慮は何が異なるのか。アクセシビリティは障害者の権利条約の9条に明記されているが、これは施設及びサービス等の利用に容易さを目指すもので、グループを対象としていて、事前に設置することが求められている。合理的配慮は権利条約の2条に定義されていて、こちらは個人対象で、要求があったときに提供する義務がある。イメージ図で紹介すると、アクセシビリティは道路の段差をなくすスロープやビール缶の点字、合理的配慮は車椅子の職員専用の机や弱視の方がセミナーに参加した際の拡大読書器、などが例として挙げられる。
DPI日本会議の取組として、差別&合理的配慮の体験談を募集し、まちの中にどのような差別があるのか、どのような合理的配慮のグッドプラクティスがあるのか、意見を集めて、障害者差別解消法の改正に繋げてきた。しかし、まだ道のりは長く、今後もこのキャンペーンを続けていなければならない。
合理的配慮の提供に必要なことは、提供する側と提供される側の対話。そして、その対話の基礎として今求められているのはコミュニケーション能力で、皆さんがどこまでできているか考えてみていただきたい。
発題③「NPO・ボランティア団体など社会課題に取り組む団体におけるハラスメント対応へのわたしたちの取り組み」/門間尚子(特定非営利活動法人mia forza 代表理事)

宮城県仙台市で活動している団体です。mia forzaは、困難を抱えている女性と子どもを応援する活動を行っており、スタッフは全員仕事をしながらボランティアで関わっている。本日は、いくつかある事業の中で、2021年度から行っているNPO・ボランティア団体におけるハラスメント対応事業(団体及び活動者のための相談対応、研修会等)について紹介する。
団体・活動者の関係づくりと応援という事業の中の柱としてハラスメント対応に取り組んでいる。皆さんには、「ハラスメント対応に関する調査報告書」と「ハラスメント予防対応実践ハンドブック」のデータをお配りしている。
これまで自身が関わってきた団体の中で、少なからずどの団体もハラスメントがあり、当時は社会的にハラスメントという認識がまだない状況だった。2015年から子ども食堂に関わっている中で、たくさんの団体からハラスメントの相談を受けるようになった。
NPO・ボランティア団体におけるハラスメント対応事業では、NPO・ボランティア団体自身が、専門家や中間支援組織と共に、自らハラスメント問題に取り組んでいくことを大切に、ハラスメントが起きた団体を糾弾するのではなく、どのように乗り越え、ハラスメントが起きない組織となっていくかを共に考え・行動したい。これまで、ハラスメントに取り組む団体へのヒアリング調査と報告書の発行、ハラスメント担当者育成研修、フォーラム開催、弁護士等へのヒアリングを基にした研究会、ハラスメント予防対応実践ハンドブックの発行、相談窓口の設置を行ってきた。
NPO・ボランティア団体は多様な関係者によって活動しているので、、ハラスメントが起きる可能性のある関係として、加害者と被害者はともに雇用関係の有無に限らないことと、誰が加害者・被害者になってもおかしくない。今日は代表的な事例として、寄付者と代表の間で起きたハラスメント事例を紹介する(※具体事例のため詳細は掲載なし。)。
NPOやボランティア団体におけるハラスメント対応の難しさとして、多様な関わり方が混在する、雇用関係がない場合はハラスメントに関する法律や制度の適用が難しい、被害者や加害者が団体や活動を辞めることでなかったことにしてしまうなど、複雑な要因がある。
ハラスメントについて組織・仲間とともに考えることとして、ハラスメントという言葉に捉われずに、組織運営や活動の中で気になることを聞き取ることを勧めている。そして、どのようなことがハラスメントなのかということをみんなで考えてみることや、自分たちは何を大切に、何を目的に活動しているのか、ということにいつも立ち返れるようにして、ハラスメントが起きないために何が必要なのか考えてみてほしい。
ハラスメントを起こさない組織を目指して、まずは風通しのよいチームづくりが大事。一方で、ハラスメントという言葉に捉われないことも重要。その他、役員の役割の見直し、外部相談機関の活用や連携、ハラスメント担当者同士が団体や地域を超えて交流する機会づくりなどに取り組んでいきたい。
●セッション2:意見交換「NSRとして取り組む人権課題」
討論「NSRとして取り組む人権課題」/松原裕樹(NNネット幹事/特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター 専務理事・事務局長)
松原:非人道性の人権を守る仕組みづくりは、地雷撤去だけでなく他の分野(核兵器廃絶など)でも応用できそうか?また、事業活動だけでなく、組織運営でも意識している人権課題や取組があれば教えてください。
吉澤:市民運動として声を挙げて国際を動かしていくところは応用できると思う。政府を動かすにしても世論が大きな力となるので、そこを市民社会が引っ張っていくことが大事。組織運営では、私たちが加害者にならないように注意している。私たちは支援する側なので、支援を受ける人にとって強い立場になってしまう場合があるので、平等であるようにセーフガーディングの勉強会などしながら気をつけている。
松原:2024年4月1日から、すべての事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。改正障害者差別解消法のポイントと私たちNPO/NGO自身が実装したい「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」についてアドバイスください。
中西:私たちは現在大きな柱として、脱施設運動とインクルーシブ教育に取り組んでいる。何でもかんでも障害者を施設に入れてしまうと、障害者の方がまちの中からいなくなってしまう。普段から障害者が身近にいる環境としてのインクルージョンが大事で、NPO/NGOが何をするかという前に、学校や地域がそのような場にしていくことが必要と考えている。
松原:誰もが持ちうるハラスメントについて、NPO/NGOが組織(役員・管理職・スタッフの役割など)として取り組みたいセーフガーディングの方法や進め方について教えてください。
門間:セーフガーディングに関して、子どもの居場所事業のスタッフ全員に研修を受けてもらっており、毎年スタッフが変わったりしていることもあるが、活動で気をつけていきたいチェック項目というのは年々増えている。セーフガーディングという視点から、対象が子どもであっても、相手がどう感じているか、日頃から声を聞くようにして、知見やルールを積み上げている。ハラスメントが起こった時は、個人対個人にしないこと、利害関係のある人でジャッジメントしないこと、線を引けるような立場の人に入ってもらって客観的に事実を押さえていくことをお願いしている。
参加者のコメント:
○ハラスメントの防止の規定や窓口の設置が取り組みやすい一歩になる。事案でなく相談レベルでも対応できる安心感になる。ただし、作って終わりでなく育てていくこと、こういう視点や取組が必要だねという改善も必要。
○人権は普遍的な問題で、NPO自身が安全であろうと思い続けているかが大事。よい活動ができているかということは重要だが、最近はKPIが活動のアウトプット重視になっているので、組織の安全性という視点が不足している。事業によって組織がどのように成長したのか、その地域がどう改善したのかという見方が必要。私達自身の安全が問われている。
○合理的配慮やハラスメントも、言葉から受ける軽さと人権侵害のバランスの悪さを感じる。地雷は核兵器の問題と似ているが、地雷の場合はそれに絞って活動したプロセスがあり、核兵器の方は政治状況から難しい問題になっている。だからこそ地雷の方は、賛同国があったり市民運動として成功した経緯がある。
○組織の中でも事業活動でも人権を考えていきたいので、素晴らしい企画で感謝しています。相手を創造することが基本で、特にハラスメントは加害も被害も身近に起こりうることで、自分自身の行いに不安を感じてしまう状況でもある。そのような不安にどう寄り添っていくのか、組織全体の共通理解にしていきたいと思う学びがありました。
総括コメント:
吉澤:人権と意識しなくても人を傷つけない当たり前の環境をつくっていきたい。NGOで働く者として、困っている人を助けるだけでなく、身近にいる人も大事にすることで、ハラスメントが一つでも減っていくと思う。
中西:周りの人を幸せにしていこうとする団体は、それをする人自身がエンパワメントされているのが望ましい。風通しのよい組織になるためには、ポジティブな近況報告から始める会議を行ったり、お互いの問題を解決できるエンパワメントが大事だと思った。
門間:組織も地域も社会も、出発点は人なので、自分の気持ちとの向き合いが重要と思っている。自己理解しながら、周りの人が何に気になっているのかシェアできる関係性があるとよい。そういう関係性が組織の中で、そして組織同士や地域の中で広がっていくと、一人ひとりの可能性や幸せを享受していくことができると思う。